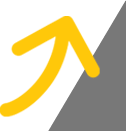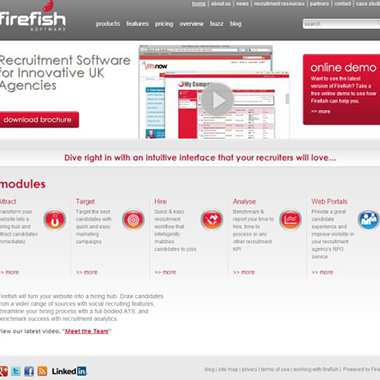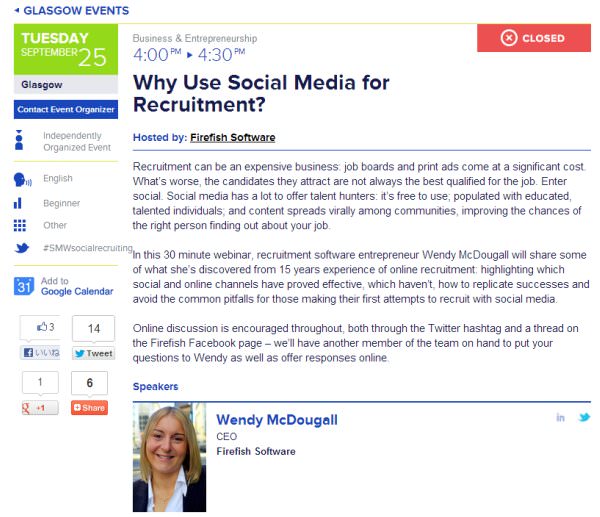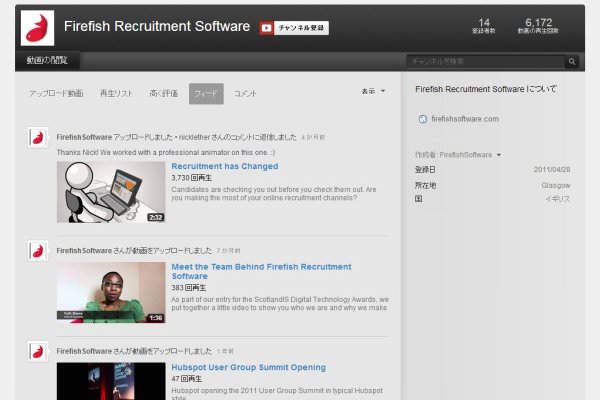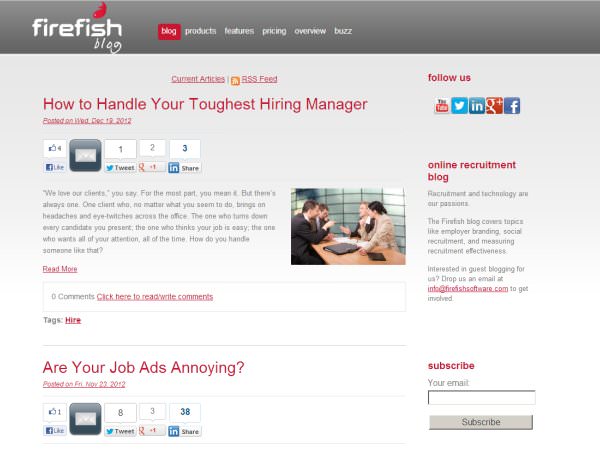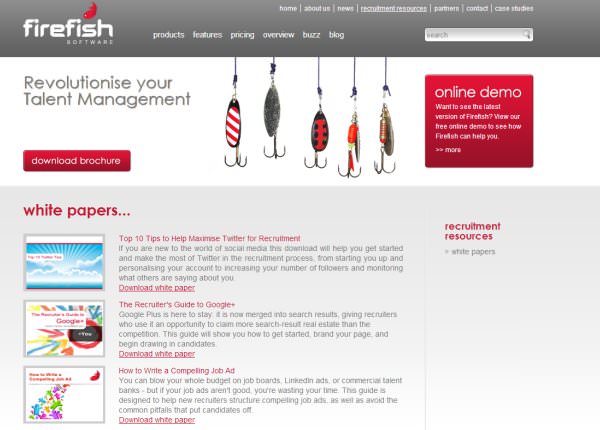【目次】
ファイヤーフィッシュ社が抱えていた課題
ファイヤーフィッシュ社では、新規開拓のために広告や展示会などのマーケティング施策に多くの予算を投じる、資金力のある大企業を相手にどう戦っていくか、というスタートアップにありがちな課題を抱えていました。
それに対して、CEOのマクドガル氏は「大企業と同じように多額の予算を費やして展示会や広告宣伝を行なっていては勝ち目はないだろう」と考えました。
インバウンドマーケティング実践の背景
ファイヤーフィッシュ社が設立されたのは2010年1月ですが、オンラインマーケティング担当役員のパートリッジ氏が参画した2011年の末には、すでにインバウンドマーケティングを行っていた同社。
いかにしてインバウンドマーケティングを実践するに至ったのでしょうか。
マクドガル氏が会社設立にあたってまず行ったのは、大手の競合がどこに予算を投下しているかを調べることでした。
その結果、資金力のある競合は展示会、DM、広告などアウトバウンド型のマーケティング手法を中心としていること。そして、価格競争が激しいソフトウェア業界では、競合に合わせて伝統的なマーケティング戦略を行なっていては収益が上がらないという結論に至りました。
では、一体どのような戦略を取るべきか。
調査をしていく中でマクドガル氏は、あるブログ記事を通してインバウンドマーケティングの存在を知りました。
ブログを読んで、インバウンドマーケティングが従来のマーケティング手法に比べ、顧客を獲得するのにかかる費用が断然安く済む手法だと気づいたそうです。
会社設立から半年経った2010年7月、予算の100%をインバウンドマーケティングに費やすことを決めました。1つのブログ記事がきっかけとなり、ファイヤーフィッシュ社はマーケティング戦略を大きく転換したのです。
 http://www.firefishsoftware.com/
http://www.firefishsoftware.com/
複数チャネルでのインバウンドマーケティング
同社が行ったインバウンドマーケティング戦略は、
- ブログ・・・月2、3本更新
- ホワイトペーパー・・・「魅力的な採用広告文を書く方法」など現在サイトに5本公開中
- ウェビナー・・・「なぜ採用活動にソーシャルメディアを使うのか」など30分~1時間のセミナーを定期開催
- ビデオ・・・YouTubeチャンネルを作り、プロモーションビデオや開発者インタビューを掲載
などの形で、顧客が役に立つと感じる、良質なコンテンツの作成を基本としていました。
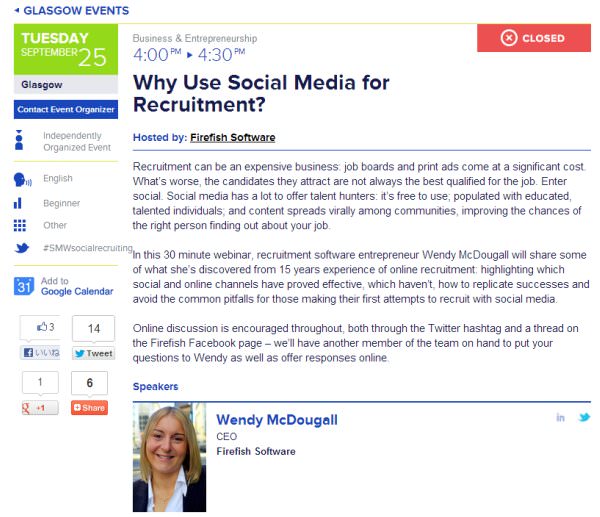 ファイヤーフィッシュ社が開催したウェビナー
ファイヤーフィッシュ社が開催したウェビナー
まず初めに、各チャネルごとに具体的な目標を設定しました。
- Twitterのフォロワー数を増やす
- Facebookのファン数を増やす
- LinkedInでは見込み顧客、顧客と交流する
- 流入に合わせて最適化したランディングページを作成する
- ウェビナー(オンラインセミナー)を開催する
上記のチャネルからどうすればコンバージョンを獲得できるかをマーケティングチームが分析しました。
また、パートリッジ氏が加入してからは、自然検索での流入を増やすために過去コンテンツの見直しなどを行い、SEOを強化。同社が最も注力をしたのは、このSEOでした。
というのも、予算の都合上、リスティング広告は行っておらず、サイトへの流入はソーシャルメディア、外部サイトからのリンク、自然検索のみだったからです。
次に、パートリッジ氏はコンテンツの強化にも乗り出しました。
「スタートアップだから、リソースは少ない。その少ないリソースを使ってコンテンツを作るのだから、最大限の効果を出したいんです。そのためにはあらゆる労力を惜しみません。例えば、ウェビナーをやるにしても、きちんと内容をメモに残す。そして、そのメモをブログの記事にするといったことをしています。」
と「何もないところからコンテンツを作る必要はない」とパートリッジ氏は話しています。
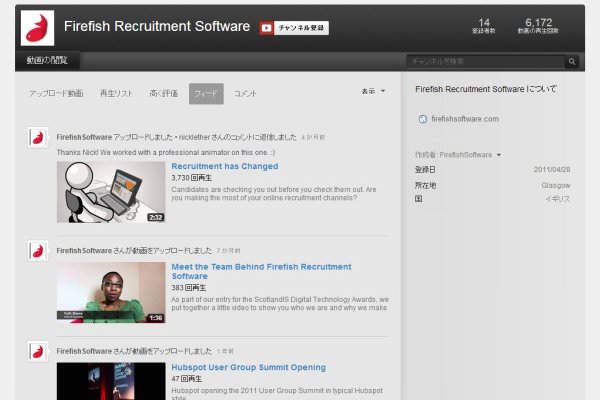 ファイヤーフィッシュ社のYouTubeチャンネル
ファイヤーフィッシュ社のYouTubeチャンネル
また、動画も積極的に活用しています。動画を作成した際は、自社のWebサイトだけでなく、ファイヤーフィッシュ社のYouTubeチャンネルにもアップします。そして、それをブログやソーシャルメディアなどの複数のチャネルで告知。トラフィック獲得、見込み顧客との接点強化の両方で良い反応が得られているようです。
自社だけでインバウンドマーケティングを完結しない
ともすると、マーケティングチームの戦略はWebサイトや自社のソーシャルメディアのみで完結してしまいがちですが、積極的に外部ともコミュニケ−ションを取っていく必要があります。
その1つが、他のサイトにブログ記事を寄稿すること。また、自分がゲストとしてブログ記事を寄稿するだけではなく、代わりに自社のブログに記事を寄稿してもらうことも行いました。
「外部へのコンテンツ投稿はやっていきたいのですが、時間がかかるため最小限にとどめています。あと、コンテンツを作ってもヒットする、しないがあって、素晴らしい結果を生むこともあれば、かなりの時間をかけて書いても、全く読まれないこともあります」とパートリッジ氏は語ります。
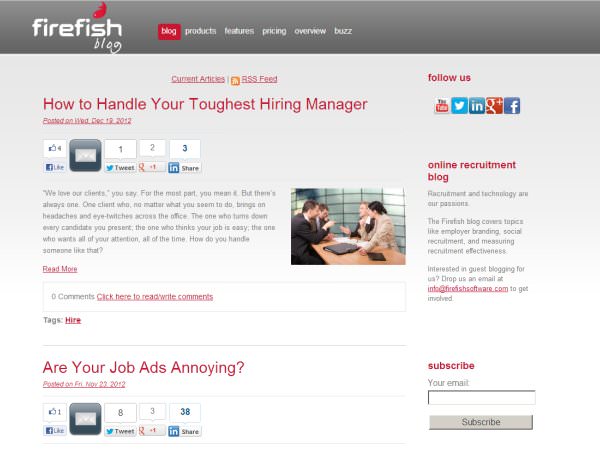 Firefish Software Blog
Firefish Software Blog
リアルよりもオンラインのイベント開催が効果的
コストがかかる展示会は、予算をかけられない会社にとっては悩みどころ。
ファイヤーフィッシュ社も展示会に出展する予算はありませんでしたが、マクドガル氏は、実際に展示会に参加しなくてもイベントを催せ、参加者とコミュニケーションを取る方法を見つけました。マクドガル氏いわく、この方法はリードの関心を高めるには非常に有効な手段でした。
「至るところでカンファレンスがありますが、オンライン上で開催すれば実際に行く必要も、お金を払う必要もありません。単にネットにつなぐだけ。オンラインの良いところは、講演者の話を聞いて、その話のポイントをまとめてブログにアップするといったことが、昼食中やカンファレンスの休憩中にできることです。そして、その記事をTwitterなどのソーシャルメディアで拡散して、参加者とのつながりを強化することができます。」
もう1つの活用法は、カンファレンスの内容をまとめたホワイトペーパーを作り、オンライン上でディスカッションのネタにすることです。カンファレンスは、本当に自社に興味がある人が参加するため、カンファレンスの情報をコンテンツとして提供することは非常に有用です。
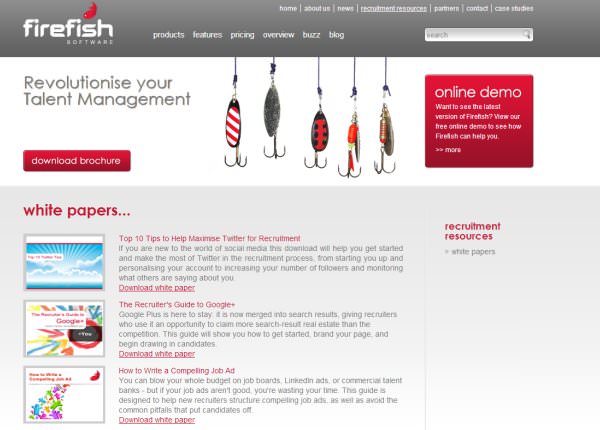 ホワイトペーパーのダウロードページ
ホワイトペーパーのダウロードページ
「オンラインカンファレンスを実施して以来、リアルの場でのセミナーや講演会には参加していません。その方がより多くのものを得られるし、Twitterのハッシュタグから他の参加者の反応を読み取るなどして、カンファレンスの流れがわかります。会場の椅子に座っているだけはわからない、俯瞰的な視点が持てるんです。」と氏は話しています。
営業よりもマーケティングに注力する
これは決して顧客を無視して、見込み顧客に注力せよ、ということではありません。ファイヤーフィッシュ社にとっては、成約見込みのない顧客を追いかける営業部隊を持つよりも、インバウンドの成果を追いかけるマーケティングチームに注力するということです。パートリッジ氏は、
「1番重要なのは、マーケティング。営業部に予算をかけるよりも、マーケティング部に予算を投下したかった。」
と明かしています。
「営業部隊には既に製品に興味があるリードのみを渡します。我々のコンテンツによって、ナーチャリングされたリードです。そうすることで、営業は製品に関心のない、まだ購入段階に至っていない顧客にアプローチする必要はなくなります。」
インバウンドマーケティングの成果
ファイヤーフィッシュ社は、リード獲得を中心にしたインバウンドマーケティングを実践していますが、リードを獲得してから、製品に興味を示すまでの間、見込み顧客とつながり続けるためにメールマーケティングも行なっています。
1年間のインバウンドマーケティング実践により、以下のような成果が出ました。
- Webサイトへの訪問数が335%増加
- リード獲得数が190%増加
- デモなどの見込み度の高いリードはそれ以外のリードに比べて1.5倍の成約率
- 顧客の維持率は94%
一方で、インバウンドマーケティングならではの問題も一つありました。
ファイヤーフィッシュ社はイギリスでのみ事業を展開しているのですが、インバウンドマーケティングであれば、インターネットを通じて世界中に届くため、アメリカからお問い合わせがあった場合には断らざるを得ませんでした。それでも、パートリッジ氏は、
「もしテレアポやDMなどのアウトバンド型のマーケティング施策を続けていたら、アメリカにいる見込み顧客にはアプローチできなかったでしょう。」
と話しています。また、
「インターネットは多くの業界にとって市場を民主化するものです。もはや広告費に莫大な予算をかけられる企業かどうか、ということは関係なくなりました。その代わり、見込み顧客は企業がオンライン上に提供する情報が本当に役に立ち、信頼できるものかに基づいて意志決定するようになりました。インバウンドマーケティングによって、コストは抑えたまま、年間の売り上げを2倍にすることができました。」
と締めくくりました。
※この記事はMarketingSherpaに許可をいただき、「Inbound Marketing: How a software company generated 190% more leads with a small budget」を翻訳し、それを元に一部を修正した記事です。